-
 Philosophy/Policy
Philosophy/Policy基本理念・基本方針
-
 Overview
Overview病院概要・沿革
-
 Planning Initiatives
Planning Initiatives行動計画と取り組み
-
 FutabaHall
FutabaHall研修講堂「ふたばホール」
-
 Shop
Shop売店
-
 Inquiry
Inquiry各種お問い合わせ
-
 Floor Map
Floor Mapフロアマップ
-
 Access
Access交通アクセス・無料バス
-
 In-hospital childcare
In-hospital childcare院内保育所「たぶの木保育所」
-
 Voice
Voice患者さんの声
-
 Donation
Donationご寄附のお願い
-
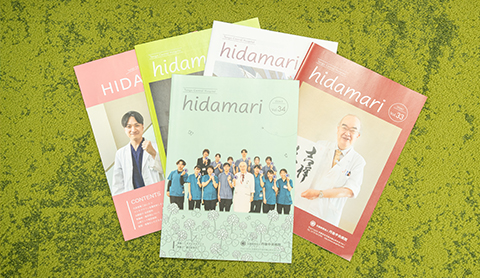 Hidamari
Hidamari広報誌 陽だまり
-
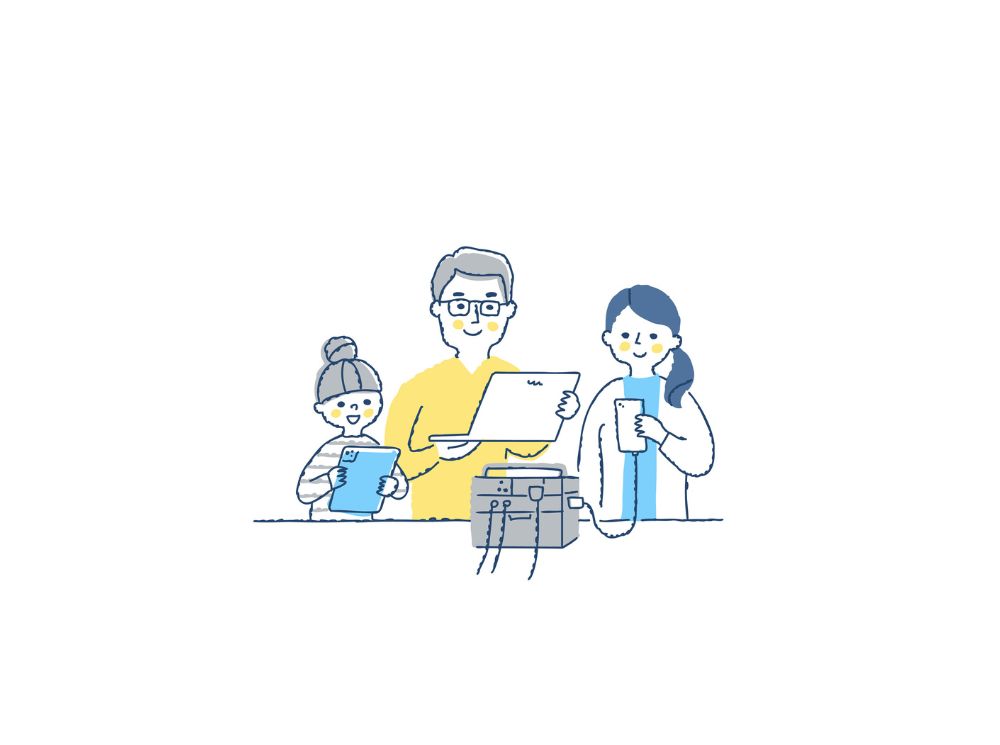 privacy
privacy個人情報の保護について
-
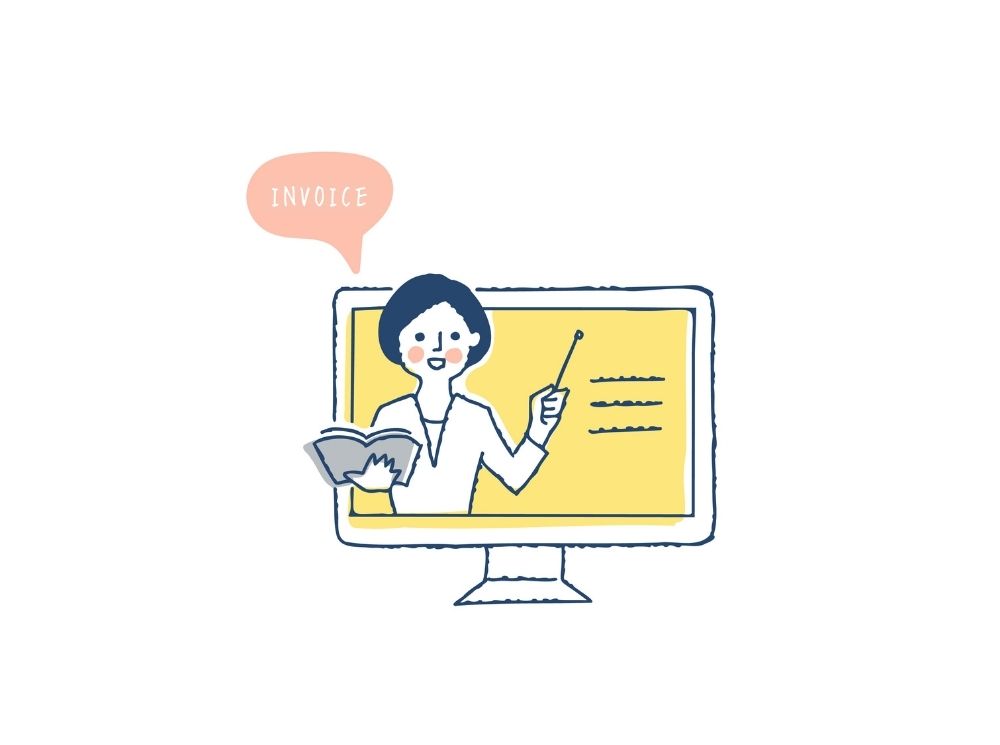 Invoice
Invoiceインボイス制度の対応について
-

人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する指針
-
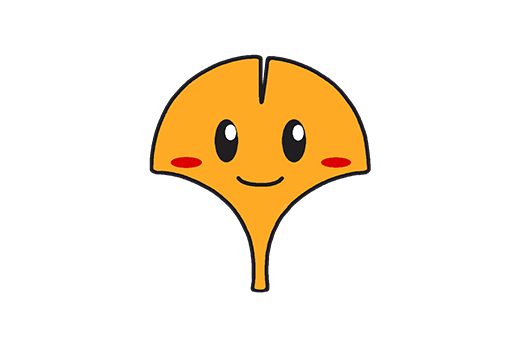
マスコットキャラクターいちょうくん

